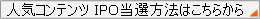IPO用語集
ネット証券 IPO比較
IPO用語集についての情報の一覧です。
IPO用語集ついての記事を順に表示します。
発行日決算取引とは、発行されてない増資新株の権利を売買するための取引。
金融クロスとは、資金調達の目的で行うクロス取引のこと。
仕出とは、「市場で売買を行う人」、「大口の買い手・売り手」、「相場師」という意味。
5%ルールとは、上場企業の5%以上を取得したら「大量保有報告書」を提出しなければならないルールのこと。
TOBとは、企業の経営権を得るために、一般株主に対して、株式の買い取りを表明・勧誘し、株式市場外での買い付けを行うこと。
公開買い付けとは、企業の経営権を得るために、一般株主に対して、株式の買い取りを表明・勧誘し、株式市場外での買い付けを行うこと。
M&Aとは、企業の合併(merger)・買収(acquisition)のこと。
しっかりとは、株価が高めの傾向のであることを指す。
締まるとは、相場が堅調な動きになり、それまで小幅に動いていた相場が高くなること。
上放れとは、取引開始時に株価が前日の値段よりも、非常に高くなった状態を指す。
強含みとは、相場がやや高く、今後も上がるだろうという気配がある状態。
上値とは、株価が500円だとすると、501円以上のこと。
つれ高とは、ひとつの株が値上がりしたときに、同じ業種の株も値上がりすること。
抜くとは、従業員が自社の株を保有することを優遇する制度。
反騰とは、下げていた相場が大きく値上がりすること。
当日決算取引とは、売買が成立したその日に決算を行います。
需給関係とは、株式市場での需要と供給を指している。
材料とは、株価を上下させる要因となるできごとのこと。
銘柄とは、株の用語としては、株式市場等で売買される有価証券の名称
こと。一般的には、商品の名称。
投資信託とは、多くの人々から集めたお金を株式や債券などに投資し、収益をあげていくことを目的とした仕組み。小額のお金でも大資産の投資と同様、多くの投資対象に分散投資でき、投資の専門家のサービスを受けられる。
投資信託では投資対象の選択をプロのファンドマネジャー(投資運用の専門家)が行う。そのため、株式や債券への投資リスクを減らし、収益をより得るようにする。
株式とは、一般的には株主であることを証明する株券のことを指す。法律上は、株式は、株式会社の株主としての権利を指す。
ちなみに、株の起源は1602年創立のオランダの「東インド会社」であると言われている。「東インド会社」は投資家から資金を得て、それを運用用の資金に使用するという当時としては画期的な方式を編み出した。
マザーズとは、東京証券取引所がベンチャー企業向けに創設した新市場。
証券総合口座とは、証券の取引以外にも使用できる口座のこと。
ザラ場とは、その日の株式取引で最初の取引と最後の取引の間の時間のこと。
普通取引とは、売買が成立してから4営業日に決済が行われる取引のこと。
ちょうちん買いとは、仕出筋や有力な投資家に便乗して株の売買をすること。
大発会とは、一年の最初の株式取引が行われる日のこと。
指し値注文とは、株式の売買注文を出す際に、投資家が株価を指定する注文方法。
売買一任勘定とは、証券会社に株式取引を任せること。
連想買いとは、特定の銘柄が買われた場合に、その好材料に連想される銘柄が買われること。
連想売りとは、特定の銘柄が売られた場合に、その好材料に連想される銘柄が売られること。
ちょうちん売りとは、仕出筋や有力な投資家に便乗して株の売買をすること。
ナンピンとは、購入した株が値下がりした場合に、あえて、同じ株を更に購入すると。
売り逃げとは、天井をうって下げに転じたタイミングで売ること。
ろうばい売りとは、相場全体がパニック状態になり、売りが続出する状態のこと。
利食いとは、購入した価格より上がった株価を売り、利益を確定されること。
日計り商いとは、一日の内に売り買いをすることにより、利益を出すような取引を指します。
いってこいとは、相場がもとの水準まで戻ることを指す。
信用取引とは、証券会社から株券やお金を借りて取引を行うこと。
追い証とは、信用取引において追加の保証金を求めること。
デイトレードとは、一日の内に売り買いをすることにより、利益を出すような取引を指します。
空売りとは、証券会社などから株を借りてきて売ること。
空売りとは、証券会社などからお金を借りてきて株を買うこと。
貸株とは、信用取引を行う際に証券会社が顧客に株を貸すこと。
IPOとは、新規に株式市場に上場すること。IPOとは、Initial Public Offeringの略。
裁量配分とは、証券会社の裁量でIPO株(新規上場株)を配分することです。つまり、証券会社の担当員が、儲けさせてもらえそうな顧客に対して、優先的にIPO株を割り当てることです。IPO取得のノウハウで裁量配分狙いが増えているようです。
関連語:抽選配分
新規公開とは、IPOと同じ意味。IPOとは、Initial Public Offeringの略。新規公開とは、新規に株式市場に上場すること。
抽選配分とは、証券会社の意図的な操作が入らないIPO株の配分の方法です。最近、新規口座を増やす手段として、IPO株(新規上場株)の抽選配分の割合を増やす証券会社が現れてきました。
関連語:裁量配分
初値とは、IPO株(新規上場株)を株式市場で公開して、初めてついた価格を指す。
関連語:公募価格
公募価格とは、IPO株(新規上場株)の上場時に、決定する株の価格です。この公募価格は、株式市場を通さずに、主幹事証券会社などから売り出されます。
IPO株投資で、この公募価格と初値の差で利益を得る投資方法があります。
関連語:初値、主幹事
主幹事会社とは、幹事会社の中でも中心となる会社。IPOにおいて、幹事会社とは、株式を新規公開する際に、株の発行・募集・売り出しを行う会社です。
主幹事会社は、もっとも、多く、IPO株(新規上場株)を引き受けるので、IPO株の申込みの時には、真っ先に申し込むべき証券会社になります。
ブックビルディング方式とは、IPO株(新規上場株)の公募価格などを決めるときに使用される方式です。IPO株の公募を行う前に、一定の価格帯を提示して、投資家の購入意向(需要)を調べて、最終的な公募価格などを決定する方式です。
なお、このブックビルディングを行う期間をブックビルディング期間(需要申告期間)といいいます。
関連語:公募価格
非上場会社とは、証券市場に上場してない会社のこと。証券市場に上場していないので、非上場会社の株式はその流動性がなく、また、どの程度の価値があるか判断しにくい。
上場基準とは、株式市場に上場するための審査基準のこと。
上場基準は、株式市場の性格により異なる。大雑把に言って、東証一部の上場基準が最も条件が厳しく、東証マザーズの上場基準が最も緩い。
募集とは、IPO株(新規上場株)を引き受けて、一般投資家に販売すること。
募集において、多数の者を相手方とする場合の「公募」と、そうではない場合の「私募」がある。一般に、50名以上の募集を、「公募」と呼ぶ。
関連語:公募、私募
公募とは、多数の者を相手方とする場合の「募集」のこと。一般に、50名以上の募集を、「公募」と呼ぶ。そうではない場合の「私募」と呼ぶ。
ちなみに、募集とは、IPO株(新規上場株)を引き受けて、一般投資家に販売すること。
関連語:募集、私募
私募とは、少数の者を相手方とする場合の「募集」のこと。一般に、50名未満の募集を、「私募」と呼ぶ。50人以上の場合の「公募」と呼ぶ。
ちなみに、募集とは、IPO株(新規上場株)を引き受けて、一般投資家に販売すること。
関連語:募集、私募
目論見書とは、IPO株(新規上場株)などを販売する際に、投資家に配布されることが義務づけられるいる書類。目論見書には、IPO株(新規上場株)などの有価証券の詳細な説明が記載されている。
訂正目論見書とは、IPO株(新規上場株)の目論見書が上場前に修正される場合に、その変更箇所を指す。
関連語:目論見書
ロックアップとは、一定期間、大株主やベンチャーキャピタル等が株式の売却などを行わないという契約をすること。IPO株(新規上場株)の公開直後の株価の下落を防ぐもの。
オーバーアロットメントとは、株式の募集・売り出しの際に、需要が募集・売り出しの数を超えている場合、主幹事証券会社が一時的に株券を借りて、売り出すこと。
冷やし玉とは、株式の募集・売り出しの際に、需要が募集・売り出しの数を超えている場合、主幹事証券会社が一時的に株券を借りて、売り出すこと。
需要積み上げ方式とは、IPO株(新規上場株)の公募価格などを決めるときに使用される方式です。IPO株の公募を行う前に、一定の価格帯を提示して、投資家の購入意向(需要)を調べて、最終的な公募価格などを決定する方式です。
需要積み上げ方式とは、ブックビルディング方式とも呼ぶ。
関連語:公募価格、ブックビルディング方式
国債とは、各国政府が発行する債券のこと。債券とは元本確定・利息確定型の証券のこと。正式名称は「国庫債券」という。
国債は、元本と利息の支払いを日本国が約束しているため、預貯金をはじめ、地方公共団体や一般の会社等が発行する債券(地方債、社債等)と比較しても、安全性は最上級に分類される。
国債の種類としては、期間1年未満の短期国債、期間5年の中期国債である割引国債、期間10年の長期国債などがある。
ストライク・プライスとは、IPO株(新規上場株)のブックビルディングにおいて、需要を申告する際の希望価格の指定方法の1つ。具体的な価格・条件を示すものではなく、どのような条件であっても購入意欲があることを示す。
関連語:ブックビルディング
引き受けとは、証券会社が、IPO(新規上場)などで、新たしく発行される株式などを発行会社から買い取り、一般の投資家に販売すること。証券会社は発行会社から手数料を受け取る。
引き受けは、「アンダーライティング」ともいう。
引き受けとは、証券会社が、IPO(新規上場)などで、新たしく発行される株式などを発行会社から買い取り、一般の投資家に販売すること。証券会社は発行会社から手数料を受け取る。
引き受けは、「アンダーライティング」ともいう。
アンダーライティングとは、証券会社が、IPO(新規上場)などで、新たしく発行される株式などを発行会社から買い取り、一般の投資家に販売すること。証券会社は発行会社から手数料を受け取る。
アンダーライティングは、「引き受け」ともいう。
公募割れとは、IPO株(新規公開株)において、初めてついた株価が公募価格を下回ること。
関連語:公募価格
株式分割とは、一つの株を複数の株式に増やすこと。株式分割すると、すでにある株式数を増やすことになる。つまり、2つに分割すると、100株持っているひとは、200株持つことになる。
株式分割により株式が増えると、配当がその分だけ増えることになる。また、数が増えても価値は変わらないので、増やした割合の分だけ株価は安くなる。安くなると購入しやすくなるので、株式の取引が活発になるというメリットがある。
株式分割しても、理論的には全体としての価値、時価総額は変わらないが、実際は、値上がりする場合が多い。
関連語:時価総額、配当
キャピタル・ゲインとは、株式自体の値上がりによる利益のこと。
関連語:インカム・ゲイン
インカム・ゲインとは、一般には、配当や利子による収入のこと。
持ち株会社とは、他の会社を支配することを目的する会社のこと。
株式持ち合いとは、旧財閥などのグループ企業等の間で、株式をお互いに持ち合うこと。
増資とは、企業が新たに株を発行して、資本金を増やすことを指す。
金融ビックバンとは、1986年にイギリスが行った金融制度改革のこと。
ヘラクレスとは、大阪証券取引所が運営するベンチャー企業向け証券市場。
従業員持ち株制度とは、従業員が自社の株を保有することを優遇する制度。
損失補填とは、株式取引等で損失を被った投資家に対して、証券会社がその損失を取り戻すこと。
第三者割り当てとは、関係の深い第三者に新株を割り当てること。
エクイティ・ファイナンスとは、新株発行・自己資本の増加を伴う資金調達のこと。
投資クラブとは、複数の人が集まって資金を出し合い、株式投資を行い、その成果を平等に分け与える組織。
成り行き注文とは、株式の売買注文を出す際に、投資家が株価を決めないで、その時の相場で取引する方法。
大納会とは、一年の最後の株式取引が行われる日のこと。
大引けとは、その日の最後についた株価。大引けは終値ともいう。
ラップ口座とは、総合的な資産運用サービスを受けられる口座。
インサイダー取引とは、公表されてない内部情報を入手した特別な人が株式取引を行うこと。
証券取引等監視委員会とは、証券市場の監視や証券会社等に対する定期検査を行う機関。
証券取引法とは、証券取引に関する基本的な事項をまとめた法律。
ディスクロージャーとは、企業が一般に対して、その経営内容を理解させるのに必要十分な内容を公開すること。
仮装売買とは、同一業者が同じ株式に対して、売買注文を出し、売買が盛んであるかのように装うこと。
風説の流布とは、意図的に虚偽の情報を流すこと。
風説の流布は、証券取引法により禁じられている。風説は、うわさのこと。
風説の流布に関しては、証券取引等監視委員会で監視している。
ジャスラックとは、これまで株式店頭市場と呼ばれていたベンチャー企業向け証券市場。
strong>オンライントレードとは、インターネットを使用した株式取引のこと。
個人投資家とは、法人でない国内の個人の投資家を指す。
手じまいとは、信用取引で証券会社から借りている資金や株券を返済すること。
反対売買とは、信用取引や先物取引で期日までに、それまでしたいた売買の反対の取引をすることを言います。
シコリとは、信用取引で損を出している買い株が多い状態を指します。
経常利益とは、決算書類で発表される利益のひとつです。
当期純利益とは、経常利益に特別利益、特別損失を加減した税引き前利益から税金を引いて算出します。
営業利益とは、損益計算書に記載してれている事項です。
保護預かりとは、証券会社が顧客から有価証券を預かって管理すること。
決算とは、企業が経営状態を把握するための会計手続きのこと。
中間決算とは、一会計期間の中間で帳簿を締め、業績を発表すること。
連結決算とは、親会社と子会社や関連会社を含めて決算すること。
売上高が前期に繰れべて増加することを増収、減少することを減収といいます。
増配/減配とは、前期よりも配当額が増えたり、減ったりしたことを言います。
財務諸表とは、企業の財務内容を表す計算書類をいいます。
損益計算書とは、会社の一会計期間における経営成績を表すものです。
営業報告書とは、決算期ごとに企業の現状を記載した書類のことです。
利益処分案とは、配当や役員賞与、社内保留分など、利益の処分方法を記載した書類のことです。
キャッシュフロー計算書とは、現金の流入と流出を記載したものです。
有価証券報告書とは、株式市場で資金を調達している会社が決算期ごとに内閣総理大臣に提出することになっています。
流動資産とは、現金に替える事ができても資産価値的には劣化する可能性があるものなどいろいろあります。
固定資産とは、1年以上の長期にわたって使用される資産のこと。
流動負債とは、貸借対照表の負債の部に記載されるものです。
固定負債とは一年以上経過した後に支払いがくる負債のことです。
法定準備金とは商法により積み立てが強制されているものです。
剰余金とは、商法が定めるもので、会社の純資産のうち、資本金および法定準備金の額を超える部分のことを言います。
未詳分利益とは、処分の対象になる利益のうち、前期に処分されなかった繰越利益と当期の利益を加えたものです。
債務超過とは、会社の負債額が資産額を超えている状態のことをいいます。
収益とは、企業外部に提供された財貨およびサービスの価値のことです。
費用とは、会社の一定期間の間に経済活動をするのに必要とした金額のことです。
デッドクロスとは移動平均線の長期線を中期線が下に突き抜けることです。
ゴールデンクロスとは移動平均線の長期線を中期線が上に突き抜けることです。
移動平均線とは、過去のある一定期間の平均株価をグラフにして売買のタイミングを計るものです。
新値足とは、新高値と新安値が出たときだけ、図表に記入する方法です。
ローソク足とは、時系列表現されるものチャートの代表的なものです。
株価純資産倍率とは、株価ょ1株あたりの純資産で割った数字です。
キャッシュフローとは、税引き後利益から配当と役員賞与を引き原価償却費を加えたものです。
株価収益率とは、株価を1株利益で割って算出します。
手口とは、どの証券会社が何株売買したかを示すみのです。
出来高とは、証券取引所での売買高のことです。出来高は株式の枚数で示します。
時価総額とは、各銘柄の株価に上場株式数を掛けたものです。
ダウ平均とは、日経平均と並んで一番なじみの深いインデックスです。
日経平均株価は、日経平均とか、日経ダウなどとも呼ばれます。
東証株価指数とは、基準日を100として、その日の時価総額がどの程度増減したかを表す指数です。
公的年金制度とは、老後の生活を安定したものにするための政府が行っている制度です。
退職給付会計とは、退職一時金と企業年金の積み立ての不足を明らかにして、その穴埋めを義務づけした会計基準のことです。
時価主義会計とは、資産を決算時点での市場価格である時価で評価しようというものです。
税効果会計とは、会計上の損益と税金の対応関係ょ財務諸表に表そうとすることです。
会社更生法とは、経営危機に陥っているが債権の可能性を持つ会社の維持・更生を図るための法律です。
粉飾決算とは、貸借対照表や損益計算書の数字を操作し虚偽の決算を行うことです。
監査法人とは、企業の決算を監査することを業務としています。
年初来高値・安値とは、1月4日から12月末までの期間に取引時間中についた最高値と最安値のことです。
1株当たり利益とは、年間に1株当たりどのくらいの利益を稼いだかという指標です。
損益分岐点とは、損益が発生する分かれ目となる売上高のことです。
自己資本規制とは、証券会社に対して金融監督庁から課せられている規制のことです。
株主資本利益率とはも株無視資本に対する税引き後利益の割合のことです。
株主資本比率とは、総資産に対する株主資本の割合のことです。
特別損失とは、その年度だけに起きた特別な費用や収益のことです。
営業外損益とは、企業の本業以外から生じる損益のことを言います。
無配とは、業績悪化によって利益がない場合、配当が行われないことを言います。
売上原価とは、製造業なら製品の製造に関する費用のことを言います。
法人投資家とは、生保・損保、銀行、投信、事業法人などの企業の投資家。
インデックス運用とは、日経平均やTOPIXなどの株価指数に連動するように売買を行う投資法。
クロス取引とは、同一証券会社がひとつの銘柄に対して、売り注文と買い注文を出して、株式取引を成立させること。
換金売りとは、お金が必要になったために、自分の株式を売ること。